| 土づくりの目的 |
|---|
|
植物は土の中に根を張ることで体を支え、水分や養分を吸収して生長します。そのため、根が生えやすく、それぞれの野菜や果物に合った土で育てることが大切です。条件さえきちんとそろっていれば、病気や害虫の被害にも遭いにくくなり、収穫まで無理なく菜園が楽しめます。まずは、育てたい野菜の好む条件を知りましょう。 |
| 土づくりの三要素 |
|---|
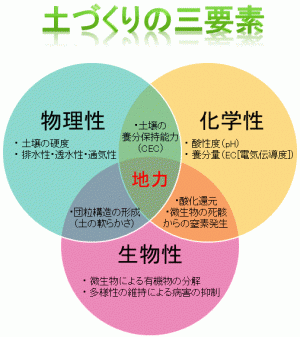 三要素とは土の物理生、化学性、生物性の働きを総合したものです。 |
| 土壌の三相分布 |
|---|
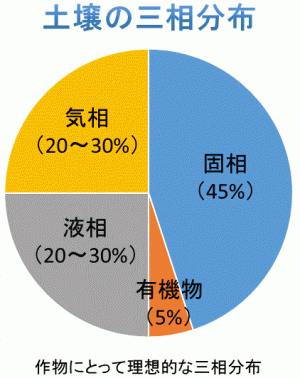 土は固体、水、空気の3つの部分で構成されています。それぞれを液相・固相・気相と言います。これらの3つの相を「土の三相分布」と言います。一般的に作物が生育しやすい土壌三相分布の比率はおよそ3:4:3になっています。 |
| 土づくりの手順 |
|---|
|
(1) 深耕する |
| 植物の必須元素 |
|---|
|
(1) 多量元素 |
| 肥料の種類 |
|---|
|
(1) 無機質肥料(化学肥料) |
| 作物に合った肥料の選択 |
|---|
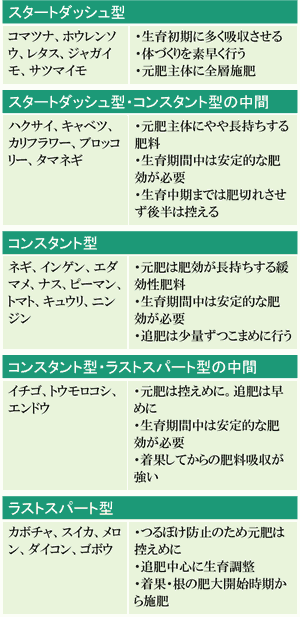 野菜は種類によって肥料の吸収パターンが異なりますので、それに応じて使い分けることが重要です。 |
| 連作障害とは |
|---|
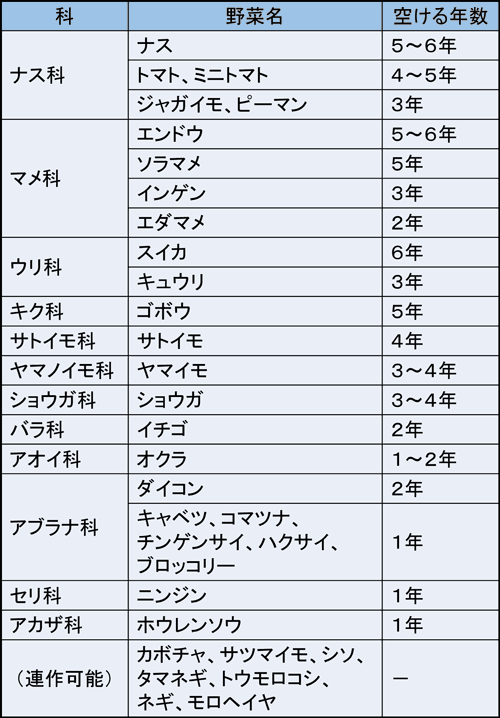 連作障害とは、同じ種類(同じ科)の野菜を同じ場所で続けて作ることにより発生する生育障害のことで、具体的には根が傷んで生育状況が悪くなったり、土壌感染の病気などで枯れてしまう現象をいいます。 |
| 連作障害の症状 |
|---|
|
<ナス科> |
| 連作障害を予防するには |
|---|
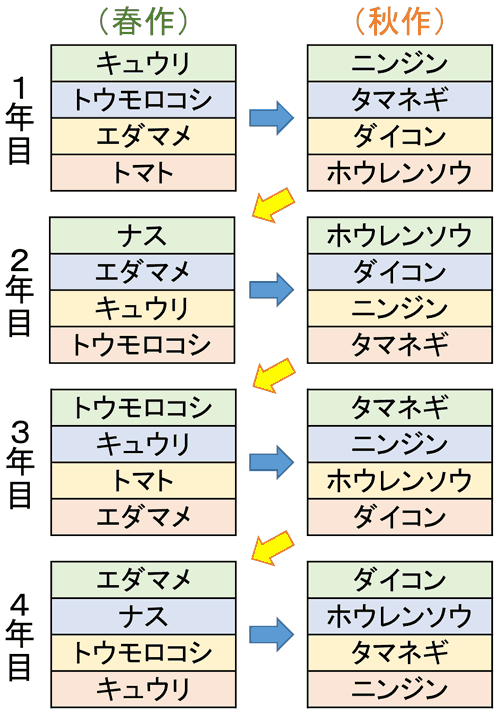 連作障害を予防するには、違う種類の野菜を順番に交代させながら栽培する「輪作」が効果的です。連作障害の出にくい野菜を輪作のローテーションに組み入れることで、他の野菜の連作障害防止にもなります。輪作のポイントは「違う科」の野菜を4年程度のローテーションで行うことです。 |
| どうしても連作する場合は |
|---|
|
<接ぎ木苗を植える> |


